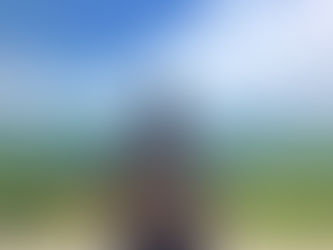株式会社資生堂 前常勤顧問、メンター三田会前会長
1964年慶應義塾大学工学部管理工学科卒、同年㈱資生堂に入社、
技術部、購買部、商品開発部、ニューヨーク駐在を経て、90年国際戦略室長、
92年取締役国際事業部長、99年取締役事業開発部長、01年執行役員常務。
主として海外事業、新規事業開発、M&Aを担当し、04年6月退任。
2021年に逝去。
過去の功績
-
ハーバード大学のイベント(Hpaire)東京大会2014を、慶應義塾大学の学生との共催。メンター三田会のメンバーも共催において、協力し、9年ぶりの東京開催を実現させた。
-
テキサス大学のI2Pコンテストにおいて、参加プランのブラッシュアップ支援を実施。2年連続入選後、テクノロジーアントレプレナーシップ部門1位を獲得。
-
慶應義塾大学が主催するデザインコンテスト「The 3rd KBC Brand-New Challenge」の開催も支援。
-
台湾やシンガポールのコンテストのブラッシュアップも支援。
-
板茂先生(当時)、松原弘典先生(当時)の2008年「四川大地震復興支援プロジェクト、成都華林小学校紙管仮設校舎建設」に協力。
森さんとメンター三田会の記憶
 2008年5月メンター三田会の打ち合わせ |  2008年5月メンター三田会の打ち合わせ |  2008年5月メンター三田会の打ち合わせ |
|---|---|---|
 2008年7月七夕祭 |  2012年3月クマールさん結婚式 |  2012年12月奨学金について学部長と懇談会 |
 2015年浜本さん結婚式 |
メンター三田会顧問
追悼サイト作成にあたり
慶應義塾大学の皆様
慶應義塾大学教職員の皆様
資生堂の常務(国際事業担当)を務められ、企業人として第一線で充実した人生を歩まれていた森さんは、��第二の人生として愛してやまなかった慶應義塾大学と後輩たちのために尽くすことを選ばれました。森さんは、お亡くなりになる前、この第二の人生が充実して豊かなものだったと振り返られていました。
慶應義塾大学の皆様
元慶應義塾大学教職員の皆様
森さんは、参加されていたSFCの國領研究会やアントレプレナーの授業を担当された教員の方たちと、授業終了後に湘南台の中華料理屋で食事をされていました。ときには大勢の学生が参加したり、ゲストスピーカーの方たちも交え、授業の延長で議論が盛り上がることもありました。
慶應義塾大学國領研OBOGの皆様
森さんは、体調を崩される前、國領研究会の授業に毎回出席されていました。学生たちの起業相談だけでなく人生相談まで、幅広くそして真摯に丁寧に学生の相談にのっていらっしゃいました。海外ビジネスプランコンテストに出場する学生の英語プレゼンテーションのブラッシュアップでは、資生堂での海外ビジネスでのご経験を活かしたアドバイスをされていました。森さんのグローバルな視点に刺激をうけて留学や外資企業で働くようになった学生たちがいます。
KBC(Keio Business Community)の皆様
2006年、SFC國領研究会のプロジェクトの1つだったビジネスコンテストを発展させて全塾の学生団体として組織化することに尽力され、その後もKBCの活動を支援されていました。学生による学生ベンチャー支援の活動がまだめずらしかった時代から、世の中に様々なベンチャー支援の取り組みが広がり、学生たちが自分たちの存在意義が見いだすことが難しくなってきた今日まで、一貫して慶應義塾とのつながりを大切にすること、学生の力を信じることを、学生に伝え続けていらっしゃいました。また、森さんは、KBCの団体を支援するだけでなく、コンテストの参加者に対しても、コンテスト後も気配りをされていらっしゃいました。
支援ベンチャーの皆様
森さんが、メンター三田会の活動として、起業の相談をうけるときには、ビジネスプランの内容より�も、相談者の想いや熱意を大切にされ、長期的な視点で、相談者にどのタイミングで何が必要かをいつも考えていらっしゃいました。森さんの頭の中には、誰に誰を紹介しよう、誰にどんな情報を伝えるかというリストとともに、起業家たちが拓く未来のイメージがありました。
慶應SFCイノベーション&アントレプレナーシップ研究コンソーシアム(KIEP)
2002年に大学発ベンチャーの研究を産学連携で行うSFC Incubation Village ConsortiumSIV)に端を欲したSFC研究所の研究コンソ―シアムの活動を通して、森さんはその豊富な人脈を生かして、国内外を問わず、学生ベンチャーや企業、メンターとの出会いを生み出すことにご尽力されていました。
メンター三田会運営スタッフ
森さんが、メンター三田会の活動として、起業の相談をうけるときには、ビジネスプランの内容よりも、相談者の想いや熱意を大切にされ、長期的な視点で、相談者にどのタイミングで何が必要かをいつも考えていらっしゃいました。森さんの頭の中には、誰に誰を紹介しよう、誰にどんな情報を伝えるかというリストとともに、起業家たちが拓く未来のイメージがありました。